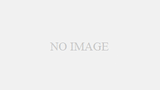1990年代の初めから2000年代の初めにかけて発生した就職氷河期ですが、2020年代になっても問題は解決していません。
どうすればよいのか、解決策を考えてみました。
就職氷河期世代救済法を制定して雇用を義務付ける
30年経っても状況が変わらないということは、就職氷河期世代救済法を制定して、強制的に解決するしかありません。
このまま放置していても、生活保護を受給する人が大幅に増えて、財政がひっ迫するからです。
それよりは、働いてもらって税金を納めてもらう方が緩やかです。
救済法の具体的な中身とは
2,000~3,000社の大手企業、高収益企業に対して、正規雇用、2億円以上の生涯賃金、勤務地の保障という条件で1社あたり3,000~4,000人雇用させます。
総務省の調査では、就職氷河期世代の非正規・無職・個人事業主を合わせた人数は800万人以上いるため、1社あたり3,000~4,000人という計算になります。
勤務先はグループ会社や取引先も含めるため、グループ会社や取引先に社会保険や諸手当などを負担させます。
相応の条件を持って雇用できない中小・零細規模の会社でも、社会保険や諸手当であれば負担できますし、本社としても負担が減るのでメリットがあります。
公務員採用も同等の条件で実施します。
教員不足は就職氷河期世代の雇用で解決する
教員不足は残業代を増やせば解決する問題ではなく、人を増やさないことには解決しません。
教員免許を持っている人の雇用を増やすか、事務員を増やす必要があります。
いづれにしても、質のある教育を提供しようとすると、携わる人はそれなりの学がある人であることが求められるので、学力の高い就職氷河期世代は打ってつけの存在です。
就職氷河期世代としても、事務系の仕事を希望している人がほとんどなので、希望にかなっています。
問題点は財源
公務員を増やす場合、予算を増やさないといけないため、財源が必要になります。
期限が決まっている国債ではなく、永久国債で対応すべきですが、国の借金は1,000兆円以上あると言われているので議論を呼ぶでしょう。
本来であれば、アベノミクスが始まった段階で、就職氷河期世代の救済も合わせて行うべきでしたが、タイミングを逃してしまったため、余計に財源という問題がクローズアップされます。
出来ることと言えば、定年延長をせずに、その枠を就職氷河期世代に譲ることぐらいでしょう。
まとめ
国が就職氷河期世代救済法を制定すれば、問題はすぐに解決します。
しかし、公務員の増員については、財源という問題が付きまとうので、実施にはハードルがあります。