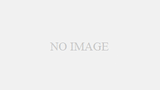正社員不足という言葉が2023年に注目されました。
その実態について、発生原因と解決策を交えて解説しました。
正社員不足とは
単純な言葉の意味としては、正社員の数が不足していることを指します。
2023年にトレンドになった言葉で、東京商工リサーチの調査によると、全体の66.5%の企業が実感しているそうです。
特に、大企業においては73.2%が正社員不足で困っているという結果が出ています。
正社員不足の発生原因
正社員不足の発生原因は複数あります。
実質的な行動制限中の解雇・離職
2020年からのコロナ禍で経済活動が制限されていましたが、2023年に行動制限が解除されたことによって、一気に表面化しました。
正社員不足に陥っているのは、飲食・宿泊・小売・福祉などライフラインを支えている仕事が中心で、コロナ禍で解雇・離職した人が多いことが原因です。
物価高による採用困難
この正社員不足に拍車をかけているのが、2023年の物価高です。
日本は輸入に頼っている国なので、外国から製品を輸入する価格が上がっているだけでなく、輸入した燃料を基に生産している製品の価格も上がっています。
そのため、国は企業に対して、賃上げを要請しています。
経営体力のある大企業は賃上げをすることが可能ですが、そうではない中小零細企業は現実的に無理だという声が上がっています。
大企業に人が流れていってしまうと、中小零細企業は経営活動に支障をきたす恐れがあり、場合によっては、賃上げ倒産が起こるでしょう。
残業規制の強化
働き方改革で残業を抑制する方向になっていますが、さらに、残業規制の強化によって、今以上に正社員の人手不足に拍車がかかる可能性があります。
それは、2024年問題と言われており、建設と物流に36協定を順守させることによって起こります。
長時間労働は本来あってはいけないので、規制は当然のことです。
しかし、納期が守れなくなるので、人を増やすか納期を伸ばすしかありません。
建設業界は外国人労働者に頼っていますが、円安によって日本で稼ぐメリットが薄れてきているため、人手が足りない状態です。
企業側の選り好み
求人募集を見ると分かりますが、企業が求めているのは35歳以下か、安く雇える定年を迎えたシルバー世代、最低賃金でも構わないパートさんです。
これらの人達が足りないというだけで、就職氷河期世代はお断りという状況です。
むしろ社内の氷河期世代を解雇して、非正規で安く使いたいという印象さえ受けます。
このような状況なので、企業の意識が変わらない限り、今後も正社員不足が続くでしょう。
正社員不足の解決策
正社員不足は社会活動に大きな影響を及ぼすので、放置してはいけません。
そこで、解決法を提案したいと思います。(物流目線で)
納期の遅延を許容する
少子高齢化で、人が足りなくなるのは止められないので、それに応じて納期の遅延を許容するのが1つ目の解決法です。
今までは、ショッピングサイトで商品を注文したら、即日~数日で届いていましたが、1週間かかっても文句を言わないというものです。
つまり、サービスに対して過剰な品質を求めないことをみんなで実践することによって、建設や物流などで働きたいと思う人を増やすことにつなげます。
フェアトレードをする
フェアトレードとは分かりやすく言うと、仕事に対して相応の対価を払うというものです。
物流であれば、消費者が送料を払う、販売元が物流会社に対して相応の費用を払うことによって、ドライバーの給与を適正な水準に引き上げることをします。
ドライバーの給与がホワイトカラーと遜色のない水準になれば、人が集まってくるので、正社員不足は解決されます。
国がエッセンシャルワーカーへ支援する
エッセンシャルワーカーと呼ばれる人達の給与は、ホワイトカラーの職種に比べて低いです。
これまでも、介護などで待遇改善の補助金を入れていますが、目立った効果は出ていません。
これは、支援する金額がまだ足りないと言えます。
そのため、公務員化するなり、補助金の金額をさらにアップするなどの対策を取ることによって、正社員として働きたい人を増やすことにつなげます。
就職氷河期世代を正当な対価で雇用する
バブル崩壊後に正社員として就職できずに、無職や非正規として働いている就職氷河期世代を正当な対価で雇用することをします。
就職氷河期世代は1970・1971~1983・1984年生まれまでで、約2,400万人います。
そのうち、少なくとも800万人以上の無職・非正規・個人事業主がいるとされているため、彼らを雇用すれば、正社員不足の問題は解決します。
当然ですが、正当な対価でないと誰も応募しないため、意味がありません。